![]()
下田に帰るたびに、必ず顔を出したい店がある。お盆のさなか、下田がいちばん賑やかになる「太鼓祭り」の晩に、うかがったその店は「花水季(はなみずき)」という。下田駅から徒歩7、8分。市街地とは逆の西本郷のはずれに、夏は白地にあずき色、冬はその逆色で掲げられるのれん。凜とした佇まいを醸しているのは、ご主人の中西孝志さんの筆による流れるような筆致で描かれた「花水季」の銘の存在感が大きい。

出会いは、偶然だった。
数年前、東京の友人を連れて、まちなかの寿司屋に入り、カウンターで地の刺身やとこぶし煮をつまみに呑んでいたら、背中越しに「ねえちゃんたち、どっから来た?」と声がかかり、東京からだというと、よく陽に灼けたおじさんから日本酒をふるまわれ、店の入り口にある水槽に手を突っ込んで、「サザエも食べな」と、港町らしい豪快なもてなしを受けた。そのおじさんチームは、下田のまちおこしNPOの集まりで、その一人に花水季のご主人がいたのだ。「呑まっせえ」「食べらっせぇ」の荒っぽい下田のオヤジたちとは異なり、眼鏡が理知的なご主人に「うちも料理屋やってるから、よかったら食べにきな」と名刺をいただいた。現金な私たちは、その翌日、さっそく開店時間の17時30分にのれんをくぐったのだ。

その日の鮮烈な印象は、いまでもはっきり思い出せる。まるで開店したての新店かと見紛うほどピカピカに磨き込まれた調理場。端正な品書きはもちろんご主人の筆。美しい盛りつけと丁寧な仕事がほどこされたつきだし。和服に割烹着がよく似合う女将さんの目端のきいたさりげない気配り……。洗練とは、こういう店のことをいうのではないか。知らない下田の一面を発見した夜であった。
※
この日、東京から来た友人と3人でうかがった。
「ごぶさたしてます」
「昨日、どうしてるかなあってちょうど話してたのよ」
透きとおるような肌の青森美人の女将さんがビールの栓を抜きながらおっしゃる。
「いつだったかな、前回来たの…」
ビールをつぎながら、ぼそっと言うと、女将さんがノートを開いて「今年の1月○日だったよ」、教えてくれる。几帳面なおふたりはだれがいつ、だれと来たかを記録しているのだ。何人もの友人を連れてきているが、ちゃんと憶えていてくれるのが客としては嬉しい。
カウンター8席に、個室になるテーブル席と座敷がそれぞれ1つ。夫婦で切り盛りするには、これがめいっぱいだろう。店の2階に住まいをかまえ、ご主人は毎朝10時には調理場に立ち、仕込みをはじめる。夕方17時30分の開店までほとんど休むことなく仕事をしているというから、語らずとも料理にかける情熱のありかはわかろうというもの。
酒肴は、地魚の刺身や煮付け、天ぷら、サザエなど、海のまちらしい品々が並ぶが、自家製がんも、豚の角煮、若どり唐揚げ、揚げ出し豆腐、茶碗蒸しなど気取らない居酒屋料理もそろい、そのどれもが格上の味だ。
私がいつも楽しみにしている、つきだしが3品並んだ。
その日の仕入れや、旬に気を配りながら、ときどきで変わる酒肴。何気ない風を装いながら、ひとくち食べて「オッ」となる人、多し。「初めてのお客さんに花水季を知ってもらおうと、つきだしにはこだわってるんだよな」と、ご主人がいつか言っていたのを思い出す。「なにこれ、うまい」。驚いている友人のとなりで、ご主人のかわりに私が誇らしげに「でしょ」となるのも常だ。
この日は、温泉卵のとろろがけ、枝豆のお豆腐、ツナサラダ。黄身と白身の固まる温度が異なることを利用してつくる温泉卵。こっくりしたとろみを維持した黄身に、ようやく固まりました、というぷるんぷるんの白身がまとっている。どうしたらこの絶妙な塩梅ができるのかと感嘆すると、65度程度を保ち30分火を通すのだという。「目が離せないから、家庭じゃなかなかできないかもね」と女将さん。たまご好き(特に黄身と白身が分かれて食べられるの)の私は、「たまごのためなら30分ぐらい、なんてことありません!」と興奮気味に言って、おふたりに笑われた。

繊細に千切りされた玉ネギ、キュウリをまとった歯触りのいいツナサラダも食欲にスイッチが入り、最初にふさわしい序奏曲。この日、目を見張ったのは、枝豆のお豆腐である。茹でた枝豆を漉し器でうらごしし、豆乳とにがりで固めたなめらかなお豆腐。涼味をさそうガラスの器に枝豆のうぐいす色が見るからに涼やかだ。つるりと口に含むと、想像以上に枝豆の味が濃く、不意打ちだった。
ビールを空にし、下田の地酒「黎明」(四合瓶)を1本とり、東京からの友人もいることだしと、地魚で刺身を盛ってもらった。「台風で海がシケたり、お盆だったりであんまり魚がないけどな」と言いながら、アジ、タコ、アオダイ、黒ムツを華やかな高台皿に盛ってくれる。(写真はいつかの、でスミマセン…)

いえいえどうして。シケとはいえ、いつもながら素晴らしい魚たちであった。装飾品の銀より輝いて見える肌に飾り包丁の入ったアジは下田ッ子のように活きがよく、口の中で弾けるほど。地ダコは磯の香りが鼻を抜け、黒ムツのよく脂の乗っていることといったら! 本当に旨い刺身に出会うと、醤油も薬味も要らず少しのワサビで十分、という気になるのだが、醤油差しは一切汚れず、「何も足さない、何も引かない」状態でいただいた。ただし、薬味好きゆえ、刺身を食べ終えてから、ちろり醤油できれいに食べ上げて満足。花水季さんのツマはご主人が糸のように細く繊細に切った大根で、ふんわりとみずみずしい。私はこれに、添えられたわさびの葉で巻いて食べる。「これだけで酒が飲める」といって、うなずいてくれる読者もいるのではないだろうか。
3、4人で訪れたときは、花水季名物の「S級サザエのエスカルゴ風」をぜひ食べていただきたい。サザエや調理法の説明は100景特集 「食菜の王国に取り上げられた下田S級サザエ」に詳しいのでそちらを参照されたし。
大人の男性の手に余るほどの大きなサザエにナイフを差し込み、手早く身を引っ張り出したご主人。さすが、痺れる職人技。肝を裏ごしし、身を薄くスライスしている間、女将さんがコンロに火を入れ、仕込んでおいたエスカルゴソースを雪平鍋で温めはじめた。ここに裏ごしした肝、サザエの切り身を入れ、混ぜ合わせる。「この塩梅は、おかみじゃないとできない。俺がやるとああならないんだよな」と珍しいことをいうご主人。女将さんにコツを聞くと、「サザエの身が縮んでから、さらに少し炒めるのがやわらかく仕上げるポイントかしら。でも、わたしも何度もやってできるようになったのよ」と謙遜する。

私は、ご夫婦ふたりで営む店で酒を飲むのが好きだ。花水季のご主人と女将さんの、こうしたさりげない相手への思いやりを感じたり、歯に衣着せぬやりとりのめおと漫才にクスッとしたり。まったく会話をせずに、黙々と仕事をしているが息が合っている夫婦とか。タイプは店によって違うが、共通するのは、生活を共にする家族にしか出せない、芯の部分でお互いに信じ合っているという安心感、ではないかと思う。
深い時間となり、ほかのお客さんも帰り、カウンターの外と内側でお酒をつぎ合っていると、ほろ酔いにまかせて「ふたりのなれそめは?」と私の友人が聞いた。ふたりは嫌な顔ひとつせず、若き日の恋物語を聞かせてくれた。
花水季のご主人は、箱根の一流ホテルや下田の料亭などで約30年腕を磨き、49歳でこの店を構えた。箱根の板前時代、仲居をしていたのが女将さんだった。あるとき、まだ20歳そこそこのご主人が、仕事はちんたらするもんじゃないと、階段を降りる時間を短縮するため2階から飛び降りた。無鉄砲がたたり、足を骨折。入院中に女将さんが見舞ったことがきっかけで、いまのふたりがあるという。
花水季は、店構えから一見、入りにくい印象を持たれるかもしれない。でも、観光客も地元客も、一見も常連も、分け隔てがないのがこの店の魅力のひとつではないかと、私は思う。
「お客が席についたときから、ヨーイドンで俺たちの真剣勝負がはじまる。味だけが店の評価になるのとは違う。どうやったら楽しんでもらえるか、満足してもらえるか。お客が帰るときの顔を見れば、その評価がわかる」
いつか、ご主人がそんなことを言っていた。
そのとなりで、女将さんも静かにうなずいていた。
この道ひと筋のふたりを、格好いいと思った。
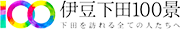
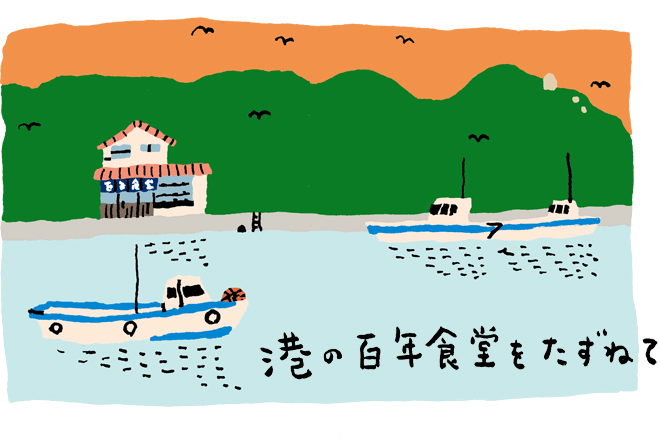
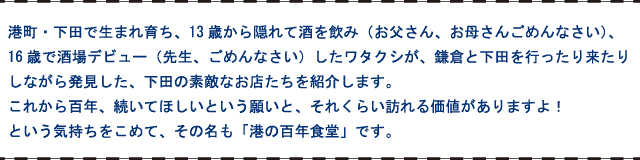




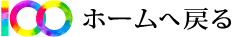
コメントする